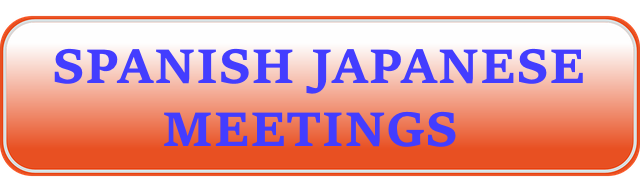明晰夢 SUEÑO LÚCIDO
Total:20760
2016/06/10
- Tam
- 2016/06/10 (v) 07:42:06
気が付くと、真っ白な何もない場所にいて、目の前には彼の緑色の目があった。
私たちの一糸まとわぬ裸体が、まるでキャラメルのようにとろけ、混ざり、まぐあい始めた。
彼が私に触れると彼の指が私の素肌に入り交じり、唇と唇が重なると、口内と舌が液体のようになっていく。
彼の目は私をとらえて離さず、このとき私は彼の所有物だったけれど、私はその状態を受け入れていた。心地いいとすら感じていたら、とうとう私の黒い瞳と彼の緑の瞳が溶け合い始めた。
どこからが私で、どこからが彼なのか。
ああそうか、私は彼のもので、彼は私のものなのだ
ついに彼のものが私のなかに入ってきた時は、すでに私たちは完璧にまざりあい、『同じもの』になっていた。彼の動きは鼓動のようで、私たちはひとつの心臓となっていた。
私たちの一糸まとわぬ裸体が、まるでキャラメルのようにとろけ、混ざり、まぐあい始めた。
彼が私に触れると彼の指が私の素肌に入り交じり、唇と唇が重なると、口内と舌が液体のようになっていく。
彼の目は私をとらえて離さず、このとき私は彼の所有物だったけれど、私はその状態を受け入れていた。心地いいとすら感じていたら、とうとう私の黒い瞳と彼の緑の瞳が溶け合い始めた。
どこからが私で、どこからが彼なのか。
ああそうか、私は彼のもので、彼は私のものなのだ
ついに彼のものが私のなかに入ってきた時は、すでに私たちは完璧にまざりあい、『同じもの』になっていた。彼の動きは鼓動のようで、私たちはひとつの心臓となっていた。